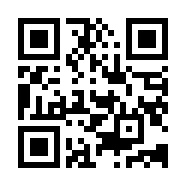職場で「楽する人が許せない!」と感じたときの考え方と対処法
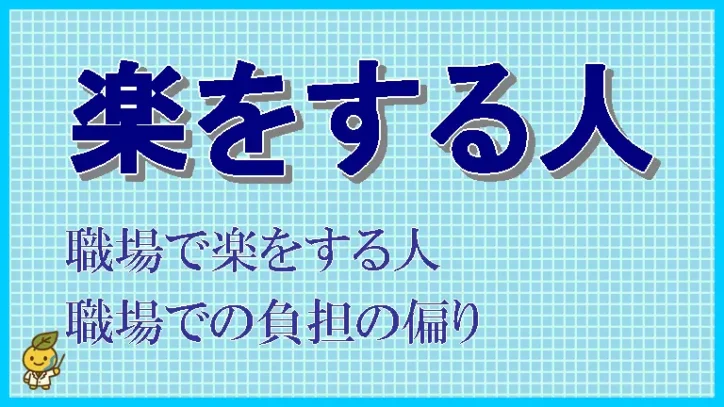
- 「なんで私ばっかり大変な思いをしてるの?」
- 「どうしてあの人は楽をしているのに、何も言われないの?」
職場で、こんなふうに 「負担の偏り」 を感じたことはありませんか?誰かが楽をすれば、その分誰かが大変な思いをするもの。
私も、職場の仕事量の差に モヤモヤを抱えた経験があります。でも、そのまま不満をため続けてしまうと、ストレスがたまるだけでなく、人間関係の悪化にもつながってしまいますよね。
では、どうすれば「楽する人」にイライラせず、問題を解消できるのか?この記事では、私自身の経験をもとに、「不公平感」を解消する考え方や対処法を考えてみました。
“楽する人”と“大変な人”の差が生むトラブル
職場で、楽をする人に対して思ったこと
職場でも、「誰かが楽をしている」と感じると、不満がたまりやすくなります。特に、自分だけが負担を多く引き受けていると、ストレスが積み重なり、関係がギクシャクする原因にもなります。
では、具体的にどんな状況がトラブルを生むのでしょうか?代表的な原因は次の3つです。
- 作業量の差
・仕事量の配分が不公平で、特定の人に業務が集中する
・いつも楽をして足を引っ張る人がいる - 楽をする人の態度
・ダラダラ作業して、なかなか仕事を進めない
・手伝いを求められても協力しない - ルールや仕組みの問題
・職場の役割分担が曖昧で、自然と負担が偏る
・仕事の評価基準が不明確で、頑張る人が損をする
実際、私もこうした状況を経験してきました。
私と同じ給料をもらっているのに、仕事が比較的簡単で手が空いている人がいました。その人は、別のチームを手伝うこともできるのに、何もしないまま時間が過ぎるのを待つだけ。一方、私のチームは常に人手不足で、まるで学園祭の前夜祭のように慌ただしく。
「きっと手伝いに来てくれるだろう」と期待していたのですが、結局一度も助けてもらえず。現場の管理者は、見て見ぬ振りをしているだけです。しかも、それが 数年にわたって続いたのです。
さらに、こんなケースもありました。ある同僚は、楽をしようとして、いつもダラダラ作業して仕事がどんどん溜まってしまいます。結局、頑張って作業を終わらせた他の作業者が、カバーにはいることに。
それだけではなく、頑張って作業を早く終わらせた人に文句をいう問題児もいました。文句を言うなら、おしゃべりしたりダラダラしないでしっかり作業して欲しいと感じました。
もしかしたら、共感された方は多いかと思います。
誰かが楽をすれば、誰かが大変な思いをする話(スポーツ編での例)
仕事と同じように、スポーツの世界でも「負担の差」は大きな影響を与えます。
同じ身長や体重の10人がいて、4段の人間ピラミッドを組む場面を考えてみましょう。この場合、最下段を避けて最上段を好むことは自然なことです。その理由は、上の段ほど負担が少ないからです。
また、別の例として綱引きを考えてみましょう。5人vs5人で行う綱引きで、1人が手を抜いた場合、残りの4人は相手の5人と勝負しなければなりません。このとき、負けないためには通常以上の力を出さなければなりません。
このように、どの場面でも「誰かの負担が増すことで、全体のバランスが崩れる」という問題が起こるのです。
楽をする人が許せない? 職場で「負担の偏り」を減らすために実践したこと
職場では、「負担の差」があると不満を感じることは少なくありません。 私自身も、「楽をする人が許せない!」と思いながら過ごしていた時期がありました。
しかし、そのままではストレスがたまる一方です。私はこの状況を変えるために、職場でいくつかの対策を実践しました。時間はかかりましたが、結果的に 職場の意識が変わり、負担の偏りが軽減されたことを実感しています。
ここでは、私が実際に試した 3つの方法を紹介します。
実践1.まずは相談する人を選ぶ
最初に取り組んだのは、職場の状況を相談できる相手を見つけることでした。
いきなり全体のルールを変えるのは難しいものです。そこで、まずは信頼できる人に相談し、小さな変化を起こすことを意識しました。
相談する相手の選び方
- 決定権のある上司に直接相談できるなら、それがベスト
- 身近にいない場合は、付き合いの長い上司や、影響力のある同僚を選ぶ
- 休憩時間などのリラックスしたタイミングで話すと、意見が伝わりやすい
実際にやったこと
私の職場では、決定権のある人に直接話せる環境がなかったため、付き合いの長い上司に相談しました。結果として、時間はかかりましたが、職場全体の意識が少しずつ変化していきました。
「手待ちの人が出ないように、みんなで協力する職場を作ろう」という方針が打ち出され、部門ごとに進捗を共有し、遅れている部署に人を貸し出すシステムができました。
ポイント:まずは「話せる人」に相談し、小さな変化を起こすことが大切!
関連記事:昇格・出世で性格や態度が豹変するような上司に誰もついてこない話
実践2.仲間を作り、協力しやすい環境を整える
どんな職場でも、協力し合える関係性を築くことが重要です。特に、「手伝いをお願いできる関係」を作ることで、負担の偏りを減らすことができます。
実践したこと
- 普段からできるだけ多くの人とコミュニケーションを取る
- 犬猿の仲の人とも、最低限の関係を維持し、敵を作らないようにする
- 自分から積極的にヘルプに入り、「次は助けてね」とお願いする
私自身、職場のメンバーと積極的にコミュニケーションを取るようにしました。作業が遅れている人がいれば、自らヘルプに入り、「次はこちらが遅れたとき、応援お願いしますね」と自然に協力を求める 形を取りました。
この積み重ねが功を奏し、「お互い様」という雰囲気が少しずつ定着していきました。
ポイント:「まず自分から手伝う」ことで、職場の協力体制を作りやすくなる!
実践3.必要なら配置転換も視野に入れる
もし、何をやっても負担の偏りが改善されない場合、思い切って配置転換を考えるのも選択肢です。
配置転換を検討するべきケース
- 現在の部署では、どうしても状況が改善しない
- 他の部署の方が、自分のスキルや働き方に合っている可能性がある
- 精神的な負担が大きく、今のままでは長く働き続けられない
配置転換を希望するときのポイント
職場によっては、「今の環境が合わない」と正直に伝えても、前向きに受け取られにくいこともあります。そこで、私は 「会社に貢献できる」というポジティブな理由を伝えることを意識しました。
- 「部署を異動し、新しい仕事もどんどん覚えていきたい」
- 「新しい部署の作業の方が、自分自身が会社に貢献できそう」
実際に、私も部署異動を依頼し、新しい環境で働くことになったことがあります。結果として、前よりも負担の偏りが少なくなり、働きやすくなりました。
ポイント:ポジティブな理由を伝え、配置転換を前向きに進める!
最終手段 見切るという選択
もし何を試してもダメな場合、環境を変えることも考えるべきかもしれません。私自身も、転職した経験があります。実際、日本では「職場の不満で転職」する人も少なくありません。
- 努力しても状況が変わらないなら、無理に我慢する必要はない
- 「この環境でずっとやっていけるか?」を冷静に考えてみる
ただし、環境を変えることが必ず正解とは限りません。でも、「ここでずっとストレスを抱えて生きていくのか?」と考えたとき、見切るのも一つの選択肢です。
[PR]:転職支援サービス Smart Career(スマートキャリア)
トラブルを起こさないように、相手を敬うこと
楽・大変の差をそのままにしておくと高確率でトラブルの原因になる
トラブルが大きくなると、人間関係が壊れたり、深刻な事態に発展することもあります。
実際に、職場や家庭内での不平不満が原因で、まれにですが殺人事件や殺人未遂事件に発展したケースはあります。。国内外で報道されることがあるため、多くの人がその事実を認識しているかもしれません。
チームや集団の中で、一部の人が他のメンバーよりも負担の差が大きい状況が続くと、恨みや嫉妬が生じ、敵意や陰口が渦巻くこともあります。このような状況には、心理的な負荷がかかり、結果として深刻な争いや暴力事件につながることがあるため、注意が必要です。
助け合うこと、協力すること
スポーツだけでなく、職場や家庭内の家事など、すべての活動はチームプレイで成り立っています。職場や家庭、スポーツにおいても、協力プレーが不可欠です。
誰かが楽をしている一方で、他の誰かが大変な目に遭う状況が頻繁に起きると、不満が募り、モチベーションが低下し、人間関係に溝が生じる可能性があります。
職場や家庭において、「大丈夫?」「手伝おうか?」といった気遣いの言葉が非常に重要です。これらの言葉があるだけで、状況が一変することもあります。相手の立場や感情に配慮し、問題が深刻化する前に早めに対処することが重要です。
自分が忙しいときほど、自己中心的な行動に走りがちで、周囲の状況に目を向けることが難しくなります。そのようなときこそ、一息ついて冷静に状況を見極め、周りに目配りをすることが重要です。
年齢を重ねると、気配りが減る?
年を取るにつれて、若い世代に比べて助け合いや気配りを忘れがちになることもあります。でも、年齢に関係なく「助け合いの意識」を持ち続けることはできます。
この記事を読んでいる皆さんに、今後も5年後、10年後、そしてその先も、相手に気配りし、負担の差が生まれないように心がけていただきたいと思います。
さいごに
職場での「負担の偏り」は、すぐに解決できるものではありません。
しかし、何もせずに我慢し続けると、ストレスがたまり、最悪の場合は職場の人間関係が崩壊してしまうこともあります。
私自身の経験から、次の3つの行動が有効だと感じました。
- 相談する人を選び、まずは小さな変化を起こす
- 仲間を作り、協力しやすい環境を整える
- どうしてもダメなら、配置転換を前向きに検討する
「自分ばかり大変」と感じたときは、何か一つでも行動を起こすことが大切 です。少しずつでも状況を変えながら、ストレスの少ない職場環境を目指していきましょう。